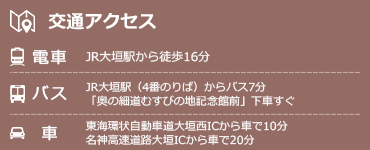俳句を詠もう
俳句は難しくありません。「俳諧は三尺の童にさせよ。初心の句こそたのもしけれ」という芭蕉のことばがあります。感じたことを素直にことばにして、まず俳句を楽しみましょう。
俳句のルール
俳句の基本ルールは2つだけ
2つの基本ルール
(1)「五・七・五」の17音で詠むこと。
(2)どこかに季節を表す言葉(季語)を入れること。
固有名詞が動かせない場合などは1音、2音多くても少なくても大丈夫!
俳句のことば「切れ字」
叙情豊かな季節感を17文字で表す、俳句の世界。「切れ字」は、普通の散文には使われていない、俳句独特のものです。「や、けり、かな」を使うことで、間をおき、その前の言葉に注意を注がせる効果があります。
「や」は、初めの五音に入れてみる。呼びかけを表現するときに使います。
「かな」は、末尾に入れて、感動を表現するときに使います。
「けり」は、末尾に入れて、断言するような強い調子を表現するときに使います。
例えば…
むすびの地川いっぱいの桜です
↓
むすびの地川いっぱいの桜かな
気持ちを表すのに切れ字を使うと俳句らしさもアップ!
俳句を作る
(1)心に浮かんだ題材を自分の言葉で表現してみる。
(2)そのあとに季語と入れ替えてみる。
例えば…
ただ母に謝りたくて手を合わす
↓
ただ母に謝りたくてバラ贈る(バラは夏の季語)
※季語はあとからでOK!季語は「あいさつ」です。感じて入れます。
【春の季語】
桜、梅、菜の花、クローバー、麗らか、立春、風船、入学など
【夏の季語】
夏の日、山開き、向日葵、海月、日焼、風薫るなど
【秋の季語】
秋の空、紅葉、コスモス、三日月、秋刀魚、爽かなど
【冬の季語】
冬の朝、枯木、粉雪、河豚、熊、寒椿など
*季語は歳時記という本などにまとめられています。
俳句を作った後は、投句してみましょう!
俳句を投句する
芭蕉と出会う街大垣「芭蕉元禄事業」の一環として、俳句づくりに親しんでいただけるよう、十六万市民投句を開催しています。
市内外問わず誰でも参加できて題も自由!気軽に俳句を作ってみませんか?
あなたの1句をお待ちしています!
俳句に触れる
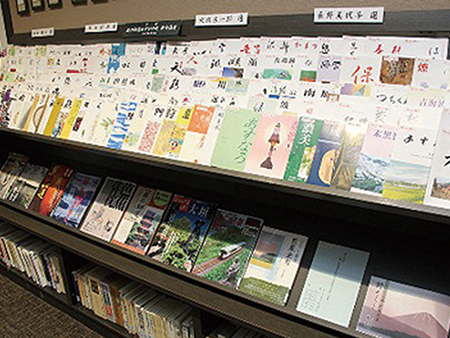
奥の細道むすびの地記念館図書コーナー
奥の細道むすびの地記念館1階の図書コーナーには、俳句に関する書籍のほか、全国の俳句結社約150団体が発行する俳句雑誌がずらりと並んでいます。全国各地の結社がよりすぐりの作品を掲載しています。ぜひ、記念館にお越しいただき、心惹かれる俳句を見つけてみてはいかがですか?
俳句をもっと知りたい!
お気軽にご利用ください!俳句なんでも相談
俳句に関する相談を随時受け付けています。「俳句を始めたい」「うまく作れない」などと悩んでいる人は、俳句指導員が相談に応じますので、お気軽にご相談ください。
○相談会場 : 奥の細道むすびの地記念館
○開設日時 : 随時(年末年始を除く) 午前9時~午後4時
※事前に同館(TEL 84-8430)へお問い合わせください